病気やケガで仕事を休んだとき
被保険者が業務外の病気やケガの治療のため、仕事に就くことができず、その期間に給料がもらえないときは、健康保険から給付金『傷病手当金』が支給されます。
傷病手当金とは
「傷病手当金」は、病気やけがで休業中の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、十分な報酬が受けられない場合に、健康保険法に基づく給付金として健康保険組合から支給される給付金です。
ただし、休んでいる期間、会社から傷病手当金の額よりも多い額の報酬を受けることができる場合には、傷病手当金は支給されません。
傷病手当金の申請については所定の申請書で行います。
支給要件
下記①~④の4条件すべてに該当しているときに支給されます。
① 業務外の事由による病気やけがの療養を目的とする休業であること
- 業務上(労務中の事案に起因する物)、通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や病気と見なされないもの(美容整形など)は支給対象外です。
② 仕事に就くことができないこと
- 病気やけがが原因で今まで就いていた仕事ができない場合で、医師の証明等を基に判断されます。
③ 連続する3日間(待期期間)を含め、4日以上休業していること
- 業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
待期の期間には、有給休暇や土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いの有無は関係ありません。
また、就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガで仕事に就くことができない状態となった場合は、その日(早退などの終日就業していない場合を含む)を待期の初日として起算することができます。
≪待期(3日間)の考え方≫
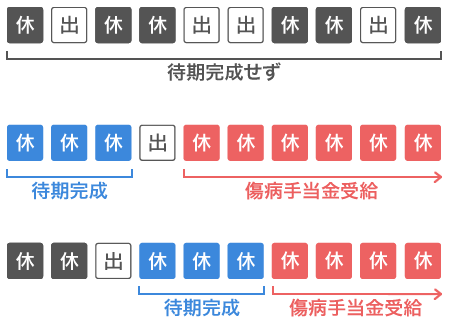
- ※1)会社を休んだ日が連続して3日間なければ成立しません。
- ※2)連続して2日間会社を休んだ後、3日目に仕事を行った場合は、「待期(3日間)期間」は成立しません。
④ 休業した期間に給与の支払いがないこと
- 傷病手当金は業務外の事由による病気やケガで休業している期間についての生活保障を行う制度のため、給与(基本給の他、各種手当金や交通費なども含めます)が支払われている期間は、傷病手当金は支給されません。
ただし、給与の支払い額が傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。 - 任意継続被保険者である期間に発生した病気・ケガについては、傷病手当金は支給されません。
支給期間について
「傷病手当金」の支給期間は、令和4年1月1日より、支給を開始した日から(支給対象となる休業期間のみを)通算して1年6ヵ月に変わりました。
ただし、支給を開始した日が令和2年7月1日以前の場合には、これまでどおり支給を開始した日から(出勤した日等を含めて)最長1年6ヵ月となります。
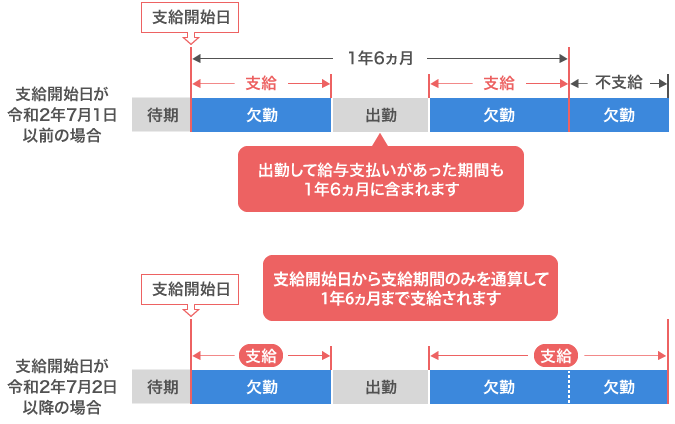
支給額について
支給対象となる被保険者の支給開始日以前の「標準報酬月額」から日額を算出し、その額の2/3を「支給日額」とします。支給額はこの「支給日額」に支給対象となる日数を乗じて求めた額になります。
ただし、支給開始日以前に12ヶ月間の健康保険の被保険者期間がない場合については、直近の連続した各月の標準報酬月額の平均額または松竹健康保険組合の前年度の9月30日時点における被保険者の標準報酬月額の平均額を使用します。
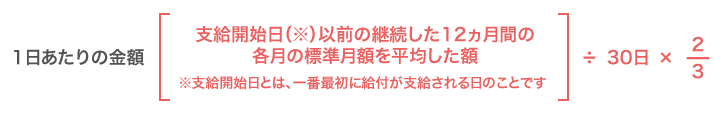
< 支給開始日以前の期間が12ヵ月に満たない場合>
支給開始日以前の加入期間が12ヵ月に満たない方の支給額は、次のいずれか低い額を使用して計算します。
- ①支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均
- ②当該年度の前年度9月30日における松竹健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額を平均した額
< 支給開始日以前に12ヵ月の標準報酬月額がある場合>
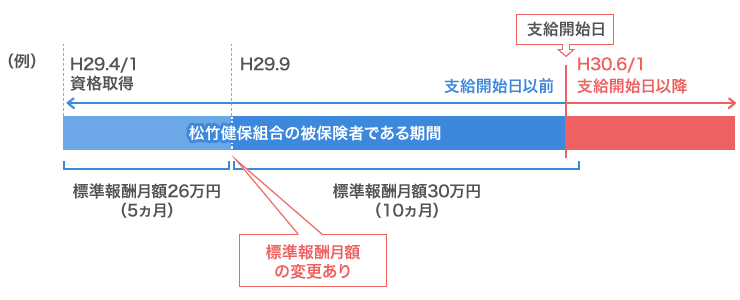
支給開始日以前の12ヵ月(H29.7~H30.6)の各月の標準報酬月額を合算して平均額を算出します。
(26万円×2ヵ月+30万円×10ヵ月)÷12ヵ月÷30日(※1)× 2/3(※2)= 支給日額6,520円
- ※1:「30日」で割ったところで1の位を四捨五入します
- ※2:「2/3」で計算した金額に小数点があれば、小数点第1位を四捨五入します。
他の給付金などを受けている場合(併給調整)などについて
≪出産手当金との調整≫
傷病手当金と出産手当金双方の受給要件を満たしている場合は、出産手当金が優先されることとなり、傷病手当金は支給されません。ただし、出産手当金の支給額が傷病手当金の額よりも少ない時は、その差額が支給されます。
≪障害厚生年金または障害手当金を受けている場合≫
条件については「障害年金について」参照
同一の病気やケガに対して厚生年金保険の障害厚生年金または障害手当金を受けている場合、傷病手当金は支給されません。ただし、障害厚生年金の額(同一の支給事由で障害基礎年金が支給されるときはその合算額)の360分の1が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額をもとに算出した額が支給されます。
また、障害手当金を受けている場合は、傷病手当金の額の合計額が障害手当金の額に達することとなる日までの間、傷病手当金は支給されません。
≪労災保険による休業補償給付との調整≫
労災保険から休業補償給付を受けている期間中は、傷病手当金は支給されません。ただし、休業補償給付の支給日額が傷病手当金の支給日額より低いときは、その差額をもとに算出した額が支給されます。
また、過去に労災保険から休業補償給付を受けていて、休業補償給付と同一の病気やけがにより労務不能となった場合には、傷病手当金は支給されません。
退職後の受給(継続給付)について
資格喪失の日の前日(退職日等)まで健康保険の被保険者期間が継続して1年(12ヶ月)以上あり(※)、被保険者資格喪失日の前日(退職日等)時点で傷病手当金を受けているか、受けられる(傷病手当金の支給要件①~③を満たしている)状態であれば、資格喪失後も支給開始日から1年6ヶ月の範囲で引き続き受給できます。
ただし、資格喪失後、1日であっても一旦就業した(仕事に就ける状態になった)場合、就業後に再度仕事に就くことができない状態になっても、傷病手当金は支給されません。
- (※)当健保組合の被保険者期間以前に他の健保組合の被保険者期間があった場合は通算して1年間(喪失・取得が連続していること)。
障害年金について(傷病手当金を受給または療養中の方)
健康保険の傷病手当金を受けている方や病気・けがで療養中の方が、障害年金の等級に該当する場合、下記の「障害年金を請求できる条件」に記載する①、②の条件のいずれかを満たせば、厚生年金保険の障害年金を請求(受給)できる場合があります。
障害年金を請求できる条件
障害年金は下記の①②のどちらかを満たせば請求できます。請求についての詳細はお近くの年金事務所、年金相談センターにご相談ください。
- ① 初診日(※1)から1年6か月後(※2)(障害認定日)に障害年金の等級に該当した場合
- ② 障害認定日(原則として初診日から1年6か月後)時点では障害状態が障害年金の等級に該当しないが、その後症状が悪化し、障害年金の等級に該当した場合(65歳以降は請求できません)
- ※1:初診日とは、障害の原因となった病気・けがについて初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいいます。
- ※2:初診日から1年6か月以内に傷病が治った場合(症状が固定した場合)は、その治った日(症状固定日)が障害認定日となります。
その他 障害年金についての詳細など
- 障害年金制度の概要については、以下の「障害年金のご案内」(リーフレット)をご覧ください。
障害年金のご案内(リーフレット)[PDF形式:260KB] - 障害年金の詳細なお手続きについては、以下の日本年金機構ホームページをご参照ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/scenebetsu/shougai.html