はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき(保険医の同意を得た場合)
はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術については、医師の同意など一定の要件を満たす場合に限り、健康保険(療養費)の支給対象となります。健康保険の適用が認められない施術については、全額自己負担となります。
健康保険の対象となるのは
≪はり・きゅうの場合≫
慢性病(下記の対象となる傷病)等であるなど、適当な治療手段がなく(医療機関において治療を行ったものの治療の効果が現れなかった場合等)、医師がはり・きゅうの施術について同意しているとき。
ただし、同時に同傷病の治療(同意のうえで必要な診察や検査を除く、処置や投薬、湿布処方等の治療)を医療機関で並行して行っている場合は給付の対象外となります。
- <対象となる傷病>
- 神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症
- ※
- 上記の他、神経痛・リウマチなどと同一範疇と認められる慢性的な疼痛についても認められる場合があります。
≪あんま・マッサージの場合≫
一律にその診断名によるものではなく、筋麻痺、筋萎縮、関節拘縮等の症状が認められ、関節可動域の拡大等、症状の改善を目的として、医療の観点からあんま・マッサージの施術が必要と医師が同意した場合に限られます。
したがって、疲労回復や慰安、予防目的などのマッサージは対象となりません。また、同傷病に対し、医療機関で医療上のマッサージを行っている場合は対象外です。
支払・申請方法について
当健保組合では、医療費適正化の観点から、はりきゅう・あんまマッサージいずれの場合も、ご本人が施術所で全額を立て替え、その後、健保組合に所定の申請をすることによって支給する方式(「償還払い」)を採用しております(※)。
療養費(家族療養費)の申請は、所定の申請書で行います。
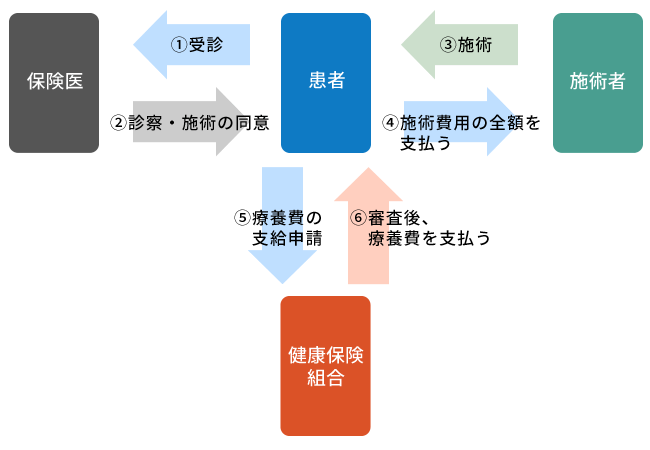
施術を受ける場合の注意点について
- ●
- 保険医による診察、同意が初回、および定期的に必要となります。
療養費の支給を受けるためには、保険医による同意が必要です。初めて施術を受けるときのほか、施術を継続する必要がある場合には、6ヶ月(変形徒手矯正術は1ヵ月)ごとに、医療機関で保険医の診察を受け、診察時の状況を踏まえて同意書を交付してもらう必要があります。
- ●
- 医療機関による治療との併用は認められません。
はり・きゅうの施術について健康保険による給付を受けることができるのは、医師が適当な治療手段がないと判断した場合のみです。はり・きゅうの施術を受けながら、並行して医療機関で同じ傷病の治療(同意の可否を判断するための診察を除く)を受けた場合、はり・きゅうの施術は健康保険の対象とはなりません。
- ●
- 施術所で記載を受けた「療養費支給申請書」の内容について、実際の施術と相違がないかよく確認しましょう。
- ●
- 必ず「領収書」を受け取り、大切に保管しましょう。